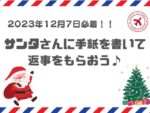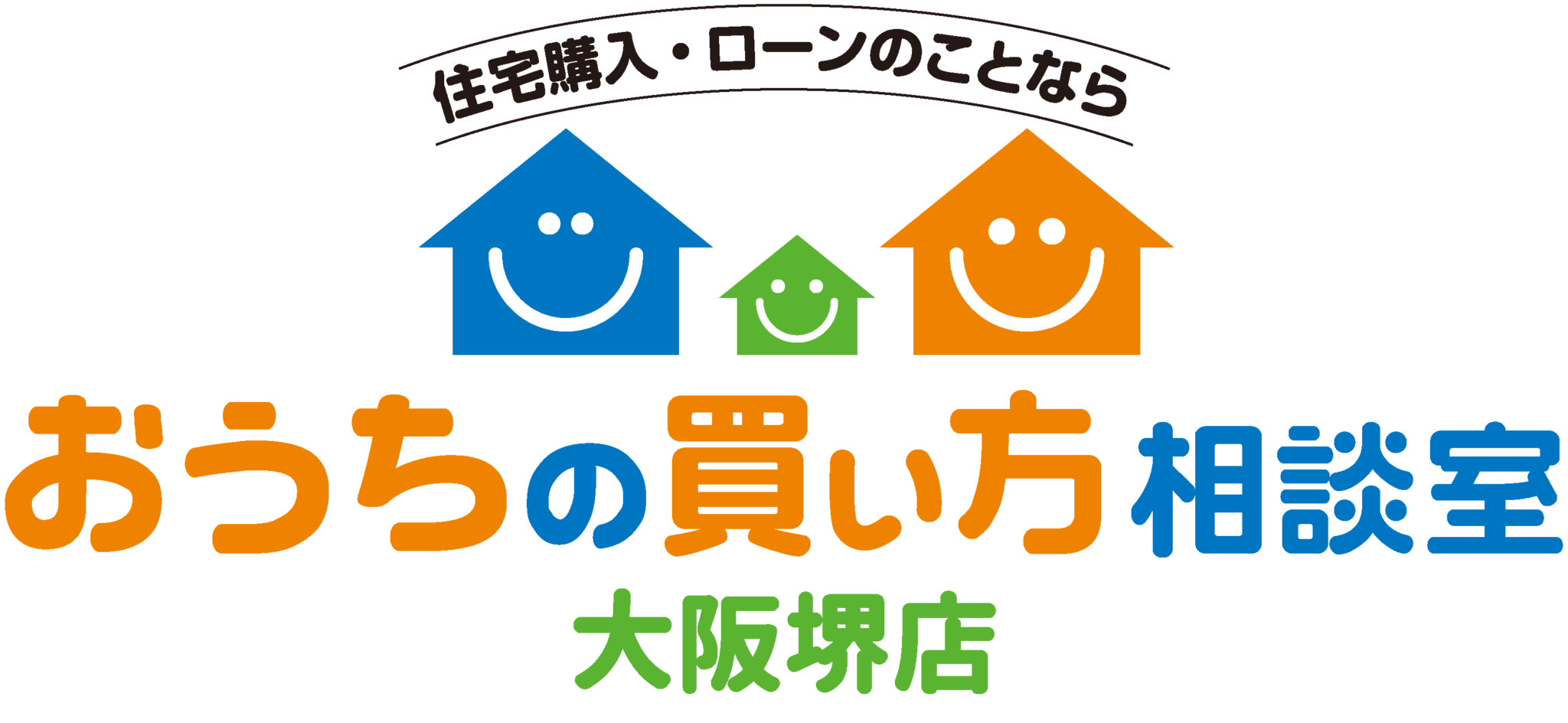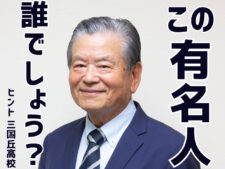【before】親子で!はじめての考古学体験♪【みよし風土記の丘in広島県三次市】
藻塩さん、初記事おめでとうございます!
初めて書いてみていかがでしたか? 最初はすごく時間がかかったと思いますが・・・慣れです笑!
だんだん早くなって、そのうち1時間くらいで書けるようになりますよ。
さて校正ですが、以下の3点を大きな基準にしています。
・伝わる日本語(基本的な文法や文章の長さ、論理性など)
・視覚的なデザイン(流し読みする読者の目をいかにとまらせるか、読みやすさのため漢字を減らすなど)
・SEO(検索で記事が上位に出てくるような対策)
これらを基準に校正した見本を、別記事(AFTER)として保存しています。
この記事(BEFORE)には赤字でコメントを入れていきますね。
わからないところやそういう意味で書いたんじゃない! ってとこがあれば遠慮なく言ってくださいね!
・アイキャッチ画像を冒頭に入れていただいているのは、OK。右の「アイキャッチ画像を設定」のところにも入れてくださいね。
・カテゴリー欄の「ライターおすすめ」は何もあてはまるカテゴリがないときに使うアンパイのような存在で、最初からここにチェックが入っています。今回は「広島県 」と「 子づれOK」「おでかけ(屋外)」に☑を入れておいてください。
・タイトルや見出しに検索ワードをいっぱい盛り込むと、そのワードで検索されたときこの記事が上位に上がってきます。
たとえば今回だと、「みよし風土記の丘 」「古墳探検ツアー 」「古墳」「広島県三次市 」などですね。
自分ならどんなワードで検索する? どんな検索にひっかかってほしい? という視点で考えてみるといいですよ。
ちなみに、タイトルに入れるのが一番効果が高く、そのあと見出し2、見出し3・・・という順ですね。
とはいえ、見出しが長すぎるのもあまりよくないです。
スマホで見る人にとっては、見出しが長いと画面ほとんど見出しみたいなことになりかねませんからね。
キーワードは入れつつコンパクトにまとめるのがポイントです!
アフターでは親子でタイムスリップ!古墳にふれる考古学デビュー「みよし風土記の丘」@広島県三次市に変更しています。
小6で習う『古墳』とは・・・
『昔の大きなお墓』です。
→タイトルと本文の間も1行空けてください
→『』は「」の中にさらにカッコをつける場合や、映画・本などの作品名の時に使用するのでAFTERでは変更しています
でも、中がどうなっているか⋯あなたは知っていますか?
亡くなった人と一緒にハニワや装飾品などが入っているのは、なんとなく知ってますが⋯
中を見たくないですか??
私は見たい!!😆
風土記の丘たんけんツアーに出発!改行

【みよし風土記の丘】にて、
10月3日〜11月18日の間、毎週日曜日13:00〜15:00で開催される
『風土記の丘たんけんツアー』
に参加しました。
→写真を挿入していただいた前後も1行空けてください。
✅️参加無料
✅️学芸員さんのガイド付き
✅️ケガをしたとき用の保険あり
↑これは、嬉しいポイントです✨
まず、室内の展示をぐるり。改行

▲教科書に出てくるハニワや武器、土器などがあります。
地形や石の棺などを見るために少しだけ見学しました。
外の天候が良くない時は、室内の展示を見て回るのも良さそう。
室内の展示をたくさん見る場合は、入館料が必要です。
AFTER記事には「みよし風土記の丘ミュージアム」「みよし風土記の丘」がどんな施設なのかの説明をいれています。
ふうどきと読みそうなとこですが、「ふどき」と読むことなど、読んだ人が「あっそうなのか」と思うようなことも入れてあげるほうが◎。
古墳を見てまわろう!
山の中にある【みよし風土記の丘】ですが、ほとんどアップダウンがなく、なだらかな道。
→タイトルのあと1行空ける
子どもと遠足気分で歩けます♪

▲なだらかなこの立地にも昔の人の思いがある?!
→正しくは「!?」です。
170個以上もある古墳は、自由に登ったり、さわったりすることができます。
※立ち入り禁止の場所もあるので、注意してください。改行

▲子どもたちは次々と古墳をかけ上がっていく。大人たちはゆっくり~
『風土記の丘たんけんツアー』では、学芸員さんがやさしくわかりやすく説明してくれるので、歴史が苦手でも大丈夫♪→『』の使用を変更しています。
「高い所にお墓を作ったのは、偉い人だとわかってほしかったから。」
「平らなところは、ハニワを並べたりお祭りをするためなんだよ。」
などなど…
「昔の人って、こんなふうに考えてたんだ…!」
と、思わずうなずいてしまうような話がいっぱい。→改行するとたしかに見やすいのですが、スマホによって1行におさまる文字数は異なるため、変な改行になって逆に読みにくくしてしまう可能性もあります。
そのため、できるだけ1行を短くし、改行なしで書き切ることをおすすめします。
AFTERは学芸員さんから教わって勉強になりましたの文章を追記しています。
まるで考古学者になったみたい♪
子どもたちは、学芸員さんからメジャーやコンパスを持たせてもらって、石の棺や部屋のあった跡のサイズや向きを測るミッションに挑戦!改行 
▲どうやったら上手く測れるかな?
追記前の「穴」だと何の穴だろうと分かりずらかったですが、部屋や棺のあとを測るのだということが分かり読みやすくなりました。
いくつかの古墳は発掘途中で、
「まだ奥に何か眠っているかも…」
とのこと。
→改行するとたしかに見やすいのですが、スマホによって1行におさまる文字数は異なるため、変な改行になって逆に読みにくくしてしまう可能性もあります。
そのため、できるだけ1行を短くし、改行なしで書き切ることをおすすめします。
これはワクワクと好奇心が止まりません✨
最近発掘されたばかりの石の部屋もあります。
内側の色は、風化によってなくなってしまうので、今しか見られない貴重なものなのだそうです。改行
→「だそうです」を使用すると、自信がない印象を与えます。言い切るようにしましょう!

▲中が赤いのはどうして?
『風土記の丘たんけんツアー』は、毎回少しずつ内容が変わるということです。
→「いうことです」を使用すると、自信がない印象を与えます。言い切るようにしましょう!
→『』の使用は、「」の中にさらにカッコをつける場合や、映画・本などの作品名の時に使用
古墳の近くには説明の看板があるのですが、むずかしい言葉もありました⋯💦
私は、家族だけで来ていたら「ふーん。」で終わっていたと思います。
なので、学芸員さんのガイド付きの『風土記の丘たんけんツアー』が大正解でした!改行
ゆっくり見たい方にはコチラ!
ガイドなしで、ゆっくり見たい方には、
マイペースにまわれるコースの案内や謎解き・探検カードも用意されています。→改行せずに1文にまとめましょう

▲小さい子でもチャレンジできそう!むずかしいバージョンもあります!
ワークショップもあり、オリジナルの勾玉アクセサリーを作ることもできます!
大人も子どもも飽きることなく楽しく過ごすことができました♪
子どもたちにも『学校で習うこと+体験』で、心に残っていてくれるといいな✨と思います。改行

▲広い芝生でおもいきり走り回るのも楽しい♪
おさんぽ日和な休日に、親子で学べる【みよし風土記の丘】に出かけてみませんか?
▼他の古墳が気になったらこちら▼
関連記事の挿入ありがとうございます。次回の記事にも藻塩さんが思う関連記事を3つくらい、いれてくださいね。
下段に施設の情報を入れるところがありますので次回も入れていただけるようお願いします。(あとで追記していただいているかと思うので、beforeでは空欄になっています。)
おつかれさまでした! 記事を書いてみていかがでしたか?
最初は慣れなくて時間がかかることも、数をこなしていけば自然とスピードアップしてきますよ♪
初めてにしてはめっちゃ上手に書けていたと思います。話の流れのもっていきかたもバッチリでした。
次回もこの調子でがんばってくださいね! 次の記事もお待ちしていまーす!
※文中にオープンチャットのバナー配置が必要なため、設定させていただいております。
(編集部対応のため、今後もご対応いただく必要はございません。)